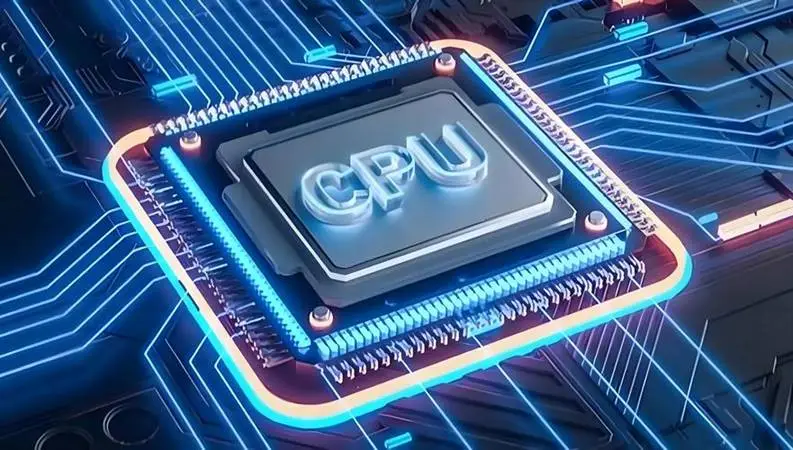中国政府は「十四五」計画において、科学技術の自立性と制御性の確保を国家戦略に位置付け、コンピューティング能力の国産化を強力に推進している。その中核を担うのが、IT国産化産業におけるCPUの開発であり、特に「実用性・制御性・安全性」を備えた情報技術体系の構築が急がれている。
現在、国産CPUは3つの技術系統に分かれる。第一はLoongson(龍芯)やSunway(申威)に代表される小規模な指令セット路線。独自性と安全性は高いが、エコシステム互換に課題を抱える。第二はPhytium(飛騰)やKunpeng(鯤鵬)が採用するARMライセンス型。モバイル生態系との連携や低消費電力の技術革新が進む。第三はx86互換路線で、Hygon(海光)やZhaoxin(兆芯)が代表的。互換性とエコシステムの成熟度が高く、特にHygon(海光)はC86命令体系を自前で拡張できる点が強みとされる。
政府調達から始まったIT国産化の流れは、政務用途にとどまらず金融・通信・エネルギーといった業界に広がり、単なるハードウェア代替から、フルスタック対応へとニーズが高度化している。これにより、CPUには単なる「使える」から「使いやすい」への進化が求められている。
その中でHygon(海光)が展開するC86体系は、Wintel互換を前提としたスムーズな移行性を実現。例えば、ある金融業や三甲病院では、x86系アプリケーションをC86プラットフォームへ移行する際のコード修正率が5%未満に収まり、低コストでの導入が可能となっている。
安全性の面でも、Hygon(海光)はハードウェア層での国産暗号アルゴリズムエンジン、OS層での信頼起動、アプリ層でのメモリ暗号化を通じて三層の防御構造を構築。安全機能を実装しても性能劣化は1%以内に抑え、かつ各世代で15〜30%の性能向上を実現している。
さらに、CPUを中核とする縦断型エコシステムの構築も進む。OSベンダーや端末メーカーとの連携により、チップ・システム・アプリケーションの統合最適化を実現。「高コスト・断片化」といった従来の課題を解消し、即時運用可能なソリューション提供を可能にしている。
Hygon(海光)のような企業による「互換性のある開放性+自律的な技術進化」モデルは、今後の国産CPU開発における重要な道筋となり得る。IT国産化は目的ではなく、情報化の一過程であることを前提に、企業にとっては「滑らかに移行できること」「安全かつ高性能であること」「自社に合った進化可能性を持つこと」が、理想的な国産化選択の条件となる。